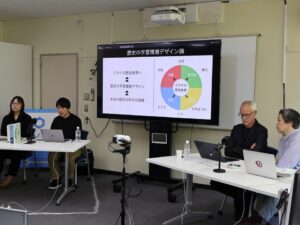【2025.04.27】定例オンラインセミナー講演会No.179「What is a historical narrative? Its importance for education(歴史的ナラティブとは何か?教育としての重要性)」を開催しました。
I.開催報告

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2025年4月27日(日)に、同研究科池尻良平研究室と川口広美研究室主催のもと、定例オンラインセミナー講演会No.179「What is a historical narrative? Its importance for education(歴史的ナラティブとは何か?教育としての重要性)」を開催しました。研究者や大学院生、学校教員を中心に、国内外から89名の皆様にご参加いただきました。
はじめに、司会の池尻良平准教授(広島大学)と川口広美准教授(広島大学)より、本セミナーの趣旨が説明されました。近年、歴史教育の研究では「歴史的ナラティブ」に注目が集まっており、歴史の語り方の種類や学習への影響に関する研究が増えていることが説明されました。一方で、日本ではまだあまり普及していない概念のため、この概念の理解を深め、歴史教育に活用することの必要性が共有されました。
- 藤原由佳特任助教(広島大学)と明月(広島大学・大学院生)
次に、ゲスト講師であるスペインのマリオ・カレテロ(Mario Carretero)教授(マドリード自治大学)が紹介され、歴史的ナラティブの研究動向と教育への活用方法について講演いただきました。また、マリオ・カレテロ教授は日本の滞在期間中に北海道や東京、広島の博物館にも訪問しており、日本の歴史的ナラティブの事例も交えながら解説いただきました。
- マリオ・カレテロ(Mario Carretero)教授
はじめに、カレテロ教授の歴史教育に対するスタンスが提示されました。カレテロ教授は、歴史教育は「何が」「どのように」起こったかを教えるだけでなく、「なぜ」起こったのかを考えることが必要であると話します。そして、この「なぜ」を語る際、語り手や語り方の影響が暗に入ります。例えば、「なぜ広島に原爆が落とされたのか」に対する説明は、国によっても語り方が違いますし、同じ日本の博物館でも語り方が違います。このような歴史の「なぜ」に関する語り方の特徴に注目したものが、「歴史的ナラティブ」の研究です。
研究の結果、歴史的ナラティブには大きく2つの種類があることが紹介されました。1つは、「個人ナラティブ」と呼ばれる、歴史上の特定の人に焦点を当てて歴史の「なぜ」を説明する語り方です。例えば、コロンブスやナポレオン、織田信長や坂本龍馬などの視点で、ある歴史の因果関係を説明する際は、「個人ナラティブ」になっているといえます。個人ナラティブは、ドラマチックな語りになりやすく、聞き手も共感しやすいため、歴史教育における動機づけの向上にはつながります。一方、ある出来事の原因が個人に集約されやすいため、政治・経済・文化的な側面まで検討する歴史学の考え方を阻害するリスクも指摘されています。
- コメントするマリオ・カレテロ(Mario Carretero)教授
もう1つが、「国家ナラティブ」です。これは、国家という集団における理想的な説明で構成されやすく、歴史的な思考をする際に問題になりやすい語り方です。国家ナラティブは、ある国におけるマスターナラティブ(支配的なナラティブ)になりやすく、以下の6つの特徴が見られることがわかっています。
①こちら側とあちら側という区別をする(アメリカ合衆国の人々はイギリスと戦った)
②認知的・感情的に自分と国を同一視させる(「我々」はイギリスと戦った)
③神話的なキャラクター、ヒーロー的なキャラクターが登場する
④「自由や領土を求める」テーマがよく出現する
⑤道徳的な要素が入る
⑥まだその国家が存在していない時代から、あたかも今の国家が昔からあるように語る(北海道や沖縄を含む「日本」地図が古代史から使われるなど)
- 藤原由佳特任助教(広島大学)と明月(広島大学・大学院生)
最後に、歴史教育への活用方法として、2つの提案が行われました。1つは、歴史の原因を生徒1人1人に語らせ、主語や動詞や話の構造の特徴を分析させてみること、もう1つは他国の歴史の教科書、博物館、映画などを比較し、自分たちが普段使っている歴史的ナラティブを批判的に振り返らせるという方法です。歴史的ナラティブは、過去を理解する際の強力なツールになるものであり、歴史教育にうまく活用してほしいと話されていました。
- ディスカッションの様子
本セミナーでは、学生や教員からの質疑応答も活発に行われました。例えば、歴史の授業で生徒のマスターナラティブを相対化させようとした際、最終的に非民主的なナラティブに固執する生徒がいた場合はどうしたら良いかという質問がされました。これに対し、カレテロ教授は「対話」の重要性を説き、誰に対しても対話が開かれており、様々な意見に触れられる教室を作ることが大事だと答えていました。
参加者からの感想としては、「歴史的ナラティブについて具体的な研究成果、経験に基づき知れるとともに、学校の歴史の授業でどのようなアプローチができるか考える機会になりました」、「教育のゴールは、対話の可能性が誰にでも開かれていること、どんな背景を持つ人でも対話の席につくことを伝えることであることなど、教育の本質に迫る貴重な言葉をいただけて大変勉強になりました。私自身が取り組んでいる教材作り、環境作りに活かしていきたいです」などが寄せられ、歴史的ナラティブの概念を共有しつつ、教育に活用するアイデアを考える刺激的な場になっていたようでした。
最後に、はるばるスペインからお越しいただき、貴重なお話をいただいたカレテロ教授に、当日の締めと同じく、スペイン語で感謝の意を述べたいと思います。
Muchas Gracias!
文責(池尻良平)
Ⅱ.アンケートにご協力ください
多くの皆様にご参加いただきまして,誠にありがとうございました
ご参加の方は,事後アンケート(アンケートはこちらをクリックしてください)への回答にご協力ください。
教育学研究科HPにも掲載されています
本イベントに関するご意見・ご感想がございましたら,
下記フォームよりご共有ください。
※イベント一覧に戻るには,画像をクリックしてください。